特定の業務における「ムリ」「ムダ」「ムラ」を排除し、経営効率を高める「業務効率化」。企業の経営課題の一つでもあり、近年ではリモートワークをはじめとする働き方の多様化に伴い、より業務効率化が重視されるようになっています。本記事では、業務効率化の概要やメリット、業務効率化の適切な進め方、促進するアイデアについて解説します。
業務効率化とは?

業務効率化とは、特定の業務におけるムリ・ムダ・ムラを取り除き、業務内容や働き方を見直して、経営効率を高めることです。具体的に、ムリとは「ムリな労働体制や業務負荷」、ムダとは「ムダな業務プロセスやコスト」、ムラとは「担当者によって手法が変わる、属人化している作業があるなどのムラ」を指します。これらの根本原因を探り、効率化に向けた取り組みを実施することで、利益の最大化を図ります。
生産性向上や業務改善との違い
業務効率化と似た言葉に「生産性向上」と「業務改善」があります。どちらも同じ意味合いで使われる言葉ですが、それぞれ目的が異なります。生産性向上は、「少ないリソース(ヒト、コスト、時間など)で多くの成果(利益、製品など)を得ること」です。「投入したリソースに対してどれだけの成果を生み出せたか、またそれがどれだけ向上したか」が指標になります。
一方業務改善は、「業務プロセス全体を見直し、より良い状態を目指すこと」が目的です。業務効率化が“特定の業務の効率化”にフォーカスしているのに対し、業務改善は“業務全体の改善”を対象としている点に違いがあります。
業務効率化が重要視される理由
昨今、業界・業種を問わず人手不足が深刻化しており、労働人口の減少や過重労働の増加などが問題視されています。こうした背景から、今までと同じ業務内容や働き方では利益を維持・最大化することが困難であるため、業務効率化が重要視されています。
業務効率化のメリット

業務効率化には、企業の経営効率を高めるさまざまなメリットがあります。主なメリットを3つ紹介します。
時間的コスト・金銭的コストの削減
これまで長時間労働が常態化していた業務を効率化することで、従業員の労働時間(=時間的コスト)と、それに伴う人件費(=金銭的コスト)を削減できます。特に時間的コストの削減は、従業員の心身負担を軽減し、モチベーションの維持や従業員満足度(ES)の向上にもつながるため、ウェルビーイング経営にも良い影響を与えます
リソースの再分配による利益の拡大
リソースの再分配とは、ある業務や部署に偏った経営資源(ヒト、カネなど)を、必要なところにまんべんなく配分し直すことを指します。経営資源は、すべてが適切に利活用されているとは限らず、前述のようにムダなコストとなっているケースもあります。それらを見直すことでリソースに余裕が生まれ、新規ビジネスの立ち上げや新たなイノベーションの創出といったさまざまなチャレンジができるようになり、利益の拡大が見込めます。
作業品質の均一化
マニュアルやフローが確立されていない、あるいは特定の従業員しか対応できないといった作業は、品質にムラが生じやすい代表例です。これらの業務を効率化することで、誰でも同じ作業を行えるようになり、作業品質の均一化が期待できます。また、属人化を解消することで、ムリな業務負荷やムダな労働時間の削減にもつながります。
業務効率化の進め方
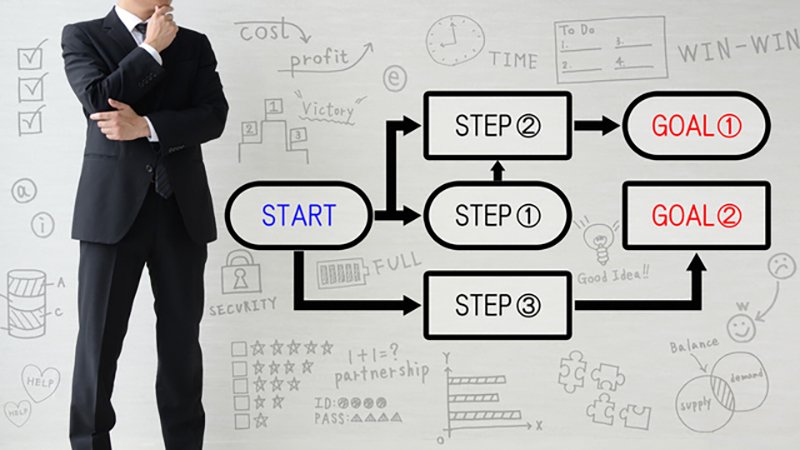
業務効率化は、やみくもに実施するのではなく、綿密な計画を立てて進めることが推奨されます。業務効率化の進め方を5ステップで紹介します。
STEP1.現状把握と課題の洗い出し
最初に行うべきは、従業員へのヒアリングなどを通じた現状の把握です。どのような業務があるのか、またその業務におけるムリ・ムダ・ムラは何かなど、業務の棚卸しを行い、課題を洗い出します。その際、担当部署やメインの担当者、業務にかかる工数などもあわせて確認しておきましょう。
STEP2.課題解決施策の検討
顕在化した課題を解決できる施策や手法を検討します。施策を実施したことでかえって業務負荷がかかってしまうことも考えられるため、業務内容の全体的な見直しが必要なのか、あるいはツールを導入するだけで解消できるのかなど、効率化が図れるかどうかもあわせて考慮することが重要です。「ムラのある施策」にならないよう、効率化すべき課題に優先順位をつけて施策を検討しましょう。
STEP3.スケジュールの立案と社内周知
施策が決まったら、実施スケジュールを立案し、内容とともに社内周知します。「施策内容」「業務範囲」「対象部署」「実施期間」などを明確にして、疑問や質問が発生した際にはすぐに回答できるような体制も整えておきましょう。ここでもムリ・ムダの排除を念頭に置き、「ムリなスケジュールを引かない」「ムダな工数をかけない」ことを意識しましょう。
STEP4.課題解決施策の実施
立案したスケジュールに沿って施策を実施します。施策の進捗状況や遅延の発生有無などを適宜確認し、進行管理を行いましょう。
STEP5.効果検証と新たな課題の洗い出し
実施期間が終了したら、定量評価と定性評価の両軸から効果検証を行います。どれくらいの業務が効率化できたのか、また従業員の業務負荷はどれだけ軽減できたのかを、ヒアリングやアンケートなどを通じて確認します。そこから得られたデータをもとに検証結果をまとめ、新たに顕在化した課題の改善施策を再検討するなどして、PDCAサイクルを回しましょう。これにより、より一層の業務効率化が期待できます。
業務効率化を促進するアイデア3選

業務効率化は、業務内容や組織体制に適した施策を実施することが重要です。業務効率化を促進するアイデアを3つ紹介します。
抜本的に業務を見直し・削減する
業務の棚卸しを行って“見える化”し、ムダな工数が発生していないかを見直しましょう。例えば、「会議に使う資料をプリントアウトして、参加者に配布する」という業務がある場合、「資料をPDF化して各自のノートPCやタブレットで確認する」「プロジェクターで投影して全員が見れるようにする」といった形に内容を変更すれば、ムダな工数を削減できます。
当たり前に行っている作業でも、見方や考え方を変えれば効率化を図ることが可能です。状況に応じて業務をなくしたり、担当者を変更するなどして、抜本的な業務の見直しや削減を行いましょう。
テクノレントでは、ノートPCやタブレットのレンタルサービスを提供しています。詳細は下記のページよりご確認ください。
業務マニュアル・フローチャートを作成する
業務の標準化・均一化のために、マニュアルを作成するのも一つの手段です。「業務品質にムラがある」「属人化している業務がある」などの場合は、マニュアルを作成して、誰でも同じ品質で業務を行えるようにすることが重要です。また、フローチャートを作成し、業務の流れを図式化してもよいでしょう。やるべき作業、やらなくてもよい作業が明確になり、業務効率が向上します。
アウトソーシングやツールを利活用する
専門性の高い業務やノンコア業務がある場合は、自社で行うよりもアウトソーシングを活用した方がコストを削減できる場合があります。業務を外部委託している時間を有効利用することで、マーケティング・営業活動や新規事業の創出といったコア業務に注力する時間を確保できます。また、定型業務を自動化できる「RPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)」などのツールを利用することも、業務効率化に有効です。
まとめ
業務効率化は、短期間で効果が表れるものではありません。重要なのは、中長期的なスパンで実施し、“中途半端に終わらせない”ことです。綿密な計画を立てた上で効果の高い業務から施策を打ち、しっかりと検証を行う。そうして新たに見えた課題を改善していく。それらを繰り返すことで、会社全体の業務効率化マインドが醸成され、文化として定着し、経営効率の向上につながります。
業務効率化でお悩みの方は、今回ご紹介した進め方やアイデアを参考に、スモールステップで始めてみてはいかがでしょうか。

