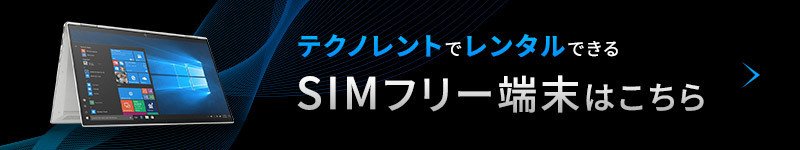営業先でのプレゼンテーションや社内ミーティングなど、ビジネスシーンでタブレットを活用する場面が増えています。中でも注目されているのが「SIMフリータブレット」です。
本記事では、SIMフリータブレットの概要や通信方式、OS・サイズ・性能による選び方、メリットとデメリット、さらにはレンタルの可否についても分かりやすく解説します。
購入を検討している方はもちろん、レンタルも視野に入れている方もぜひ参考にしてください。
SIMフリータブレットとは?

タブレットには主に2つの通信方式があります。「モバイル通信タイプ」と「Wi-Fiモデル」です。それぞれの通信方式について見ていきましょう。
モバイル通信タイプ
1つ目は、iPadの「セルラーモデル」や「LTEタイプ」と呼ばれる、スマートフォンと同じ通信規格のモバイル回線が利用できるタブレットです。これらはSIMカードを挿入することで、Wi-Fiのない環境でもインターネットに接続可能です。一般的にこのタイプが「SIMフリータブレット」と呼ばれます。
Wi-Fiモデル
2つ目は、Wi-Fiを利用して通信するモデルです。比較的安価で販売されていますが、SIMカードスロットがないため、Wi-Fi環境下でしかインターネットに接続できません。モバイルWi-Fiルーターなどがないと、使える場所が限定される点には注意が必要です。
SIMフリータブレットの種類

SIMフリータブレットにはさまざまなOS、サイズ、性能があり、何を決め手に選べば良いか迷うこともあるでしょう。ここではSIMフリータブレットを選ぶ際のポイントについて解説します。
タブレットの選び方
●OSで選ぶ
OS(Operating System)は「基本ソフトウェア」といい、タブレットの基本的な操作やアプリを使うためのソフトウェアを指します。SIMフリータブレットには以下3種類のOSがあります。
- iOS(Apple)
- Android(Google)
- Windows(Microsoft)
●iOS(Apple)
iOSの特徴は、セキュリティが強固ということや、クリエイティブ系のアプリが豊富であることが挙げられます。またiPhoneやMacなどApple社製品との連携もスムーズです。ただしiOSが搭載されているタブレットはiPadのみとなり、端末価格も少し割高です。
●Android(Google)
Androidの特徴は、製品のバリエーションが豊富な点です。またニーズに合わせて自由に設定をカスタマイズできるのもメリットです。ただしiOSに比べてセキュリティ面のリスクが少し高いためウィルス対策など注意が必要です。
●Windows(Microsoft)
Windowsの特徴は、PCのWindowsと同じソフトウェアを利用できることで、ビジネス利用での相性がよいOSです。ただし他のOSと比べてエンタメ系のアプリは少ない傾向にあります。
●サイズで選ぶ
SIMフリータブレットには大きく「約7インチ」「8〜9インチ」「10インチ以上」の3つに分けられるため、利用シーンに合わせて適切なサイズを選びましょう。例えば、ウェブサイトやメールのチェックなど個人利用の多い場合はコンパクトな7インチ、訪問先でタブレットを提示する機会が多い場合は大きめの10インチ前後を選ぶと良いでしょう。
・約7インチ
SIMフリータブレットの中でも、もっとも小さなサイズとなり、軽くてコンパクトなため、外出先での使用が多い方に向いています。ただし画面が小さいため、文字や映像が見づらくなってしまいます。
・8〜9インチ
画面が大きく、文字や映像が見やすくなるため、取引先や商談での資料提示の際に便利です。ただし7インチより一回り大きいため、片手では持ちにくく、価格もやや割高となります。
・10インチ以上
SIMフリータブレットの中では一番大きなサイズとなります。ビジネスユースとしてはこの10インチ前後が最も多く利用されており、細かな文字や表、図解、資料などが見やすくなります。ただし重量があるため持ち運びにくく、価格も割高となります。
●性能で選ぶ
OSとサイズの他に、性能面についてもしっかりとチェックしておきましょう。性能面とは主に「CPU」と「ストレージ」です。
CPUとは、Central Processing Unitの略で、SIMフリータブレットの計算処理能力に大きく関わります。一般的にCPUの性能が高いほど操作性が快適になり、低いほど処理スピードが遅くなります。動画編集などの作業が多い場合は、できるだけCPUの性能が高いものを選びましょう。
次にストレージですが、これは写真・動画・音楽・アプリなどのデータ保存容量のことで、「GB」で表されます。
この数値が大きいほど大量のデータを保存できます。タブレットはパソコンとは違って後から内部ストレージを増設することができません。このため、たくさんデータを保存しておく必要がある場合は、あらかじめストレージの大きいモデルを選びましょう。
それでもストレージ容量が不足しそうなときは、クラウドストレージサービスの利用を検討したり、Android端末であればmicroSDカードに対応した機種を選んだりするなど、購入前に十分な検討を行うことをおすすめします。
その他にも、例えば外出先での利用が多い場合、バッテリー容量も重要です。いつでも充電できる環境とは限らないため、大容量バッテリーのモデルを選ぶとよいでしょう。
SIMフリータブレットのメリット・デメリット

ここからはSIMフリータブレットのメリット・デメリットについて解説します。良い点と注意したい点それぞれを理解したうえで導入を検討しましょう。
メリット
SIMフリータブレットのメリットは、なんと言ってもSIMカードを挿入すれば場所を選ばずインターネットに接続ができる点です。デザリングを行ったり、Wi-Fiルーターを購入したりする必要がなく、端末一台だけで完結します。
また各通信事業者が販売しているモバイル通信可能なタブレットと比較しても、多くの選択肢があり、低価格の端末を探すことも可能です。海外のSIMカードも利用できます。
さらにSIMロックがかかっていないため、キャリア変更も自由に行えます。通信プランの見直しや格安SIMなどの使用で通信コストを抑えることができ、経費の削減にも結びつきます。
デメリット
SIMフリータブレットのデメリットとして、SIMロック付きやWi-Fiモデルのタブレットと比べて本体価格が高く、導入時の初期費用が大きくなる傾向があります。たとえば、Wi-Fiモデルなどで、大手通信事業者と契約する場合は、下取りキャンペーンやキャリア独自の分割払いが利用できるため、初期費用を抑えやすくなっています。
一方、SIMフリータブレットではこうしたサービスがあまり提供されておらず、支払いは基本的に一括かクレジットカードでの分割払いに限られる点に注意が必要です。
また、端末によっては対応していない回線があることもデメリットの一つです。機種にもよりますが、海外製のSIMフリータブレットには、日本の通信事業者が提供する回線に対応していないものがあります。事前に通信事業者の「動作確認端末一覧」を確認しておきましょう。
また、大手通信事業者でタブレットを購入する場合に比べると、SIMフリータブレットは故障した際の修理や代替機などのサポート体制が提供されていません。
SIMフリータブレットをレンタルするという選択も
ここまでSIMフリータブレットの購入前に知っておくべき種類や選び方などをお伝えしてきましたが、端末をレンタルすることも可能です。
レンタルを活用すれば、初期費用を抑えられるだけでなく、万が一端末に不具合が生じた場合でも、サポートを受けられる安心感があります。また、OSやサイズ、CPU、ストレージなどの仕様を変更したい場合でも、買い替えることなく希望スペックの端末に乗り換えられるのも大きな利点です。さらに、使用期間が限られている場合には、利用後に返却できる点もレンタルならではのメリットと言えるでしょう。
SIMフリータブレットの導入をご検討の際は、購入とレンタルの両面から比較検討することをおすすめします。
なお、テクノレントでは、Windows 10 Proを搭載した10.5インチおよび14インチのSIMフリータブレットをご用意しています。ストレージ容量も128GBと256GBからお選びいただけるため、ビジネス利用に最適な1台がきっと見つかります。
まとめ

SIMフリータブレットは、Wi-Fi環境がなくてもインターネット接続が可能な、非常に利便性の高い端末です。種類や特徴も多岐にわたり、メリットだけでなく留意すべきデメリットも存在します。購入とレンタルの両方を視野に入れつつ、ご自身のビジネスシーンに最適な1台を選びましょう。