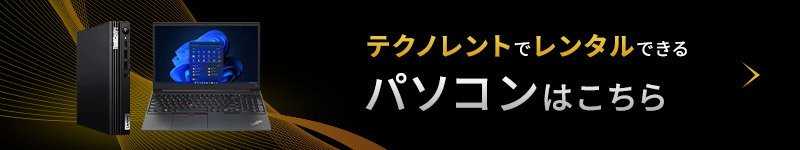会社でパソコン(PC)を導入するときは、すぐに利用できるように「キッティング」という作業が必要です。キッティングには手作業で1台ずつ行う方法と、マスターイメージを作成して複数台にコピーするクローニングという方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自社でキッティングを行う際は状況に合わせて選択しましょう。
本記事では、キッティング作業の手順や注意点などを解説します。
キッティングとは

キッティングとは、パソコンを導入する際に、すぐに仕事ができる状態に設定する作業のことです。
キッティングとセットアップの違い
「キッティング」とよく似た言葉に「セッティング」がありますが、両者は作業範囲に違いがあります。
セットアップはOSのインストールまでが作業範囲ですが、キッティングはOSの設定、業務に必要なプログラムやアプリケーションのインストールなども行い、すぐに仕事に取りかかれる状態にする作業のことです。
つまり、キッティング作業の中にセットアップも含まれています。
キッティングには2つの方法がある
先述の通り、キッティングには1台ずつ手作業で行う方法と、マスターイメージを作成して複数台にコピーするクローニングという方法があります。
手作業は台数が少ない場合に適した方法です。パソコンが手元にあればすぐに作業を始められます。しかし、1台ずつ手作業で行うため、人為的なミスが発生しやすいことや、1台あたりの人件費が高くなることがデメリットといえます。
一方、クローニングは導入台数が多い場合に適した方法です。マスターイメージをコピーするため、一度に大量のパソコンをキッティングできて、作業効率が向上をできます。
もしパソコンが故障した場合は、マスターイメージを使って代替機を用意できることもメリットの一つです。
ただし、マスターイメージの作成や検証には数週間〜1カ月程度かかることや、作業にあたる担当者に専門知識や経験、技術力が必要になるといったデメリットもあります。導入する機種が多い場合は機種ごとにマスターイメージを作成する必要があるため、さらに作業時間がかかります。
このように1台ずつ手作業でキッティングする方法と、クローニングにはそれぞれメリット・デメリットがあるので、状況に合う方法を選びましょう。基本的にはパソコンの台数が少ない場合には手作業、キッティングする台数が多い場合はクローニングが向いています。
キッティングの手順

ここでは、キッティングを「手作業で行う場合」「クローニングで行う場合」のそれぞれの手順を解説します。
手作業で行う手順
1台ずつ手作業でキッティングするときは、主に次の手順で行います。
- パソコンを用意して開梱、通電確認
- ログインユーザーの作成
- ホスト名、IPアドレスなどを設定
- 業務用アプリケーションのインストールやライセンス認証
- セキュリティ設定、省エネ設定、ブラウザ設定
- セキュリティパッチの適用
- 管理番号ラベルの貼付、管理台帳への記帳
クローニングで行う手順
パソコンの台数が多い場合は、クローニングで行うと効率よく作業ができます。クローニングで行う手順は次のとおりです。
- マスターPCの設定
- SYSPREP(Microsoft)コマンドでの一般化を実施
- マスターイメージの抽出
- パソコンのブートオーダーの変更
- クローニング
- 個別キッティングの実施
- 動作評価の実施
- 管理番号ラベルの貼付、管理台帳への記帳
キッティングを自社で行うときのポイント

キッティング作業は手間がかかるためアウトソーシングする方法もありますが、自社で行う場合は以下のポイントに留意しましょう。
事前準備をしっかり行う
キッティングは単純な作業ですが、作業項目が多いため、事前準備をしっかり行うことが大切です。特にクローニングの場合はマスターイメージに設定ミスがあれば、コピーしたすべてのパソコンでアプリケーションが使えないなどの大きな問題が発生します。ミスが発生しないように作業手順書を作成し、検証作業のチェックシートで作業漏れがないか確認しましょう。
スケジュールに余裕を持つ
キッティングの台数が多ければ、作業に時間がかかります。予期せぬトラブルが発生すると作業が中断するため、スケジュールどおりに進まない可能性も考えられます。導入する期日までに作業が完了しないという事態を防ぐため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。キッティングを行う人員も余裕を持って計画しておきましょう。
セキュリティ対策を徹底する
キッティングを行う際は、セキュリティ対策の徹底が必要です。業務に関係のない有害サイトの閲覧や、アプリケーションのダウンロードによってウイルスに感染すると、機密情報や個人情報が漏えいする恐れがあります。顧客の個人情報が漏えいすれば、会社は信用を失ってしまいます。
キッティングを行う際は万全のセキュリティ対策を実施しておきましょう。具体的な対策としては「特定のアプリ以外は使用できなくする」「紛失・盗難した場合のためにロック機能を付ける」などの対策が挙げられます。
マスターPCを作成するときの注意点
大量のパソコンをキッティングする場合はクローニングを採用することになるでしょう。クローニングに必要なマスターPCを作成するときの注意点を解説します。
ボリュームライセンスを購入する
クローニングでマスターPCを作成する際は、ボリュームライセンスに付随する再イメージ権が必要です。忘れずにボリュームライセンスを購入しておきましょう。再イメージ権がないままマスターPCから複数台にOSをコピーすると、ライセンス違反になってしまうため注意が必要です。
プリインストールされたWindowsで作成しない
パソコンにプリインストールされているWindows OSは、そのパソコンに対してのみ使用が認められたOEMライセンスです。ほかのパソコンへのクローニングには使用できないため、注意しましょう。ボリュームライセンスメディア(ISO)の入手が必要です。
ライセンス認証回数の上限を増やしておく
キッティングは機器ごとにライセンス認証を行う必要があります。クローニング時はライセンス数が不足しないように、ライセンス認証回数の上限値を必要な数まで増やしておきましょう。上限値はMicrosoft社やライセンス購入元に申請すれば変更できます。
申請を忘れて作業を始めると、キッティングの最中にライセンス認証が通らず、作業が遅れてしまいます。ライセンス数の上限値はキッティングを始める前に増やしておきましょう。
個別キッティングの注意点

マスターPCからコピーした後、個別にパソコンをキッティングする際の注意点を解説します。
インベントリ情報の収集
パソコンはIT資産のため、管理が必要です。ホスト名やIPアドレス、シリアル番号、MACアドレス、ディスク容量などのインベントリ情報は、社内で配布する前に収集して記録しておきましょう。
資産管理ソフトを導入する場合は、パソコンを利用者に配布した後でも収集可能です。
設定結果を保存しておく
設定の詳細情報を保存しておくと、設定ミスや漏れなどが発生したときに確認できます。特に個別キッティングの情報は、パソコンごとに整理しておきましょう。
管理ラベルを貼る
キッティングしたパソコンは、配布前に管理番号やホスト名を記載した管理ラベルを貼り付けておくことも大切です。不具合が起こった際、パソコンの利用者が管理ラベルを見て管理番号を伝えれば、どのパソコンに問題が起きているか把握できます。管理ラベルを貼り付けておけば、資産を棚卸する際も個体を識別しやすくなります。
テクノレントはキッティングの代行が可能
テクノレントは法人向けのパソコンやタブレットのレンタルサービスを行っています。お客様に合わせた設定やキッティングを代行できるため、すぐに使える状態で納品可能です。故障時もキッティング済みのパソコンを最短即日配送いたしますので、作業がストップする期間を最小限に抑えられます。
キッティングは手間がかかる上に、ミスが許されない作業のため、担当者にとっては大きな負担となるでしょう。キッティング作業済みのレンタルPCを導入すれば、すぐ作業に取りかかれます。
まとめ
まとまった台数のパソコンを導入する場合、社内でキッティング作業するとIT担当者の業務量が増え、負担になってしまいます。効率よくキッティングを行うには、アウトソーシングを検討するのもおすすめです。
テクノレントでは、長期から短期まで法人向けのパソコンレンタルを行っています。設定やキッティングからデータ消去までワンストップで全て対応できますので、ぜひお気軽にご相談ください。